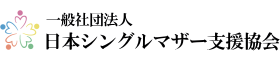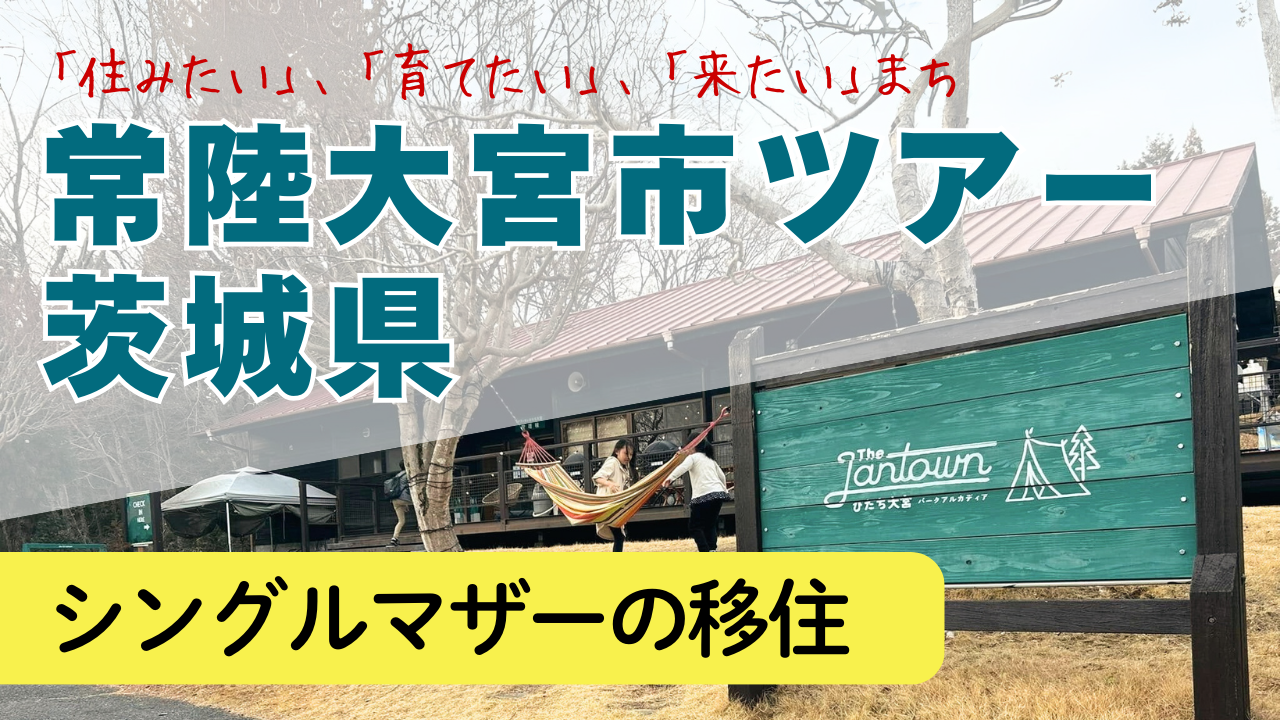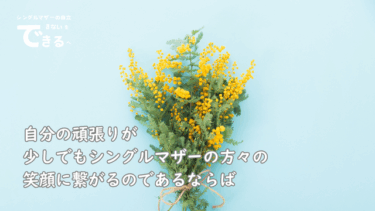「シングルマザー=貧困」という思い込みを超えて ― 支援現場から見える本当の課題

■“ひとつのイメージ”に縛られる危うさ■
シングルマザー支援の現場に12年関わる中で痛感しているのは、「シングルマザーは大変」という固定観念が、支援や社会の理解を狭めているということです。
確かに、大変さはあります。けれど同時に「気が楽になった」と感じる人もいます。多様な姿があるのに、社会はどうしても“ひとつの側面”で語りたがる。その結果、見えない現実が置き去りにされてしまいます。
■「シングルマザー=貧困」という誤解■
報道などでよく目にする「シングルマザーの半数が貧困」という数字。事実ではありますが、その背景や構造は十分に理解されていません。
実際には、夫婦がそろっていても貧困家庭は数多く存在します。むしろ、家庭の貧困が離婚の引き金となり、その延長線上に「貧困のシングルマザー」が生まれているケースも少なくないのです。
にもかかわらず、「シングルマザー=貧困」と括られてしまう。これは、全体像のわずか一部を切り取って「これがシングルマザーです」と提示しているようなものです。主婦に多様な姿があるように、シングルマザーにも多様性がある。その前提を欠いた議論や施策は、本質からずれてしまいます。
■必要なのは「生活力を育てる支援」■
本当の課題は、「生活困窮に陥らなくてもよい人までが困窮してしまう」状況にあります。ここを変えるためには、就職支援や教育を通じて、生活力を持てる環境を整えることが欠かせません。
長らく「女性が働かないのは自然」とされてきた社会の空気は、いまだに支援現場に影を落としています。けれど今こそ見方を変えなければなりません。働く力を身につけ、可能性を広げられる環境が整えば、シングルマザーは“支援を必要とする存在”ではなく、“社会を支える存在”になります。
社会や支援者が「見方を変える」こと。そこから未来は確実に変わっていきます。