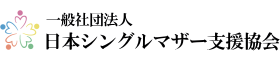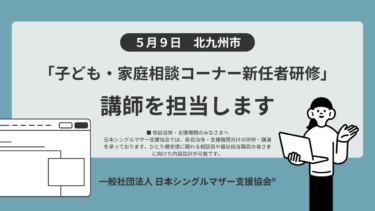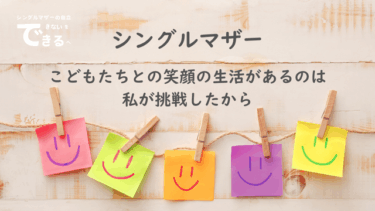~公正証書と養育費保証で「見守られている安心」を~
2025年4月19日(土)に、「離婚アレコレセミナー」を開催しました。
今回は「養育費の取り決め」や「法廷養育費制度」、そして「公正証書」や「養育費保証制度」の活用方法について、経験談を交えながら学びを深めました。
セミナーの主な内容
● 養育費の現状
日本では、子どもの未来を守るための養育費が十分に機能していない現実があります。
- 養育費の取り決めがあるのは全体の約半数
- 実際に受け取れているのは3割以下
- 未払いに対して海外のような厳しい罰則がない
● 2026年導入予定「法廷養育費」について
この制度は、離婚時に一定の基準に基づいた養育費を自動的に決定する仕組みで、現在、導入に向けて国が動いています。当協会も法務省よりヒアリングを受け、最新情報を共有しています。
学びのポイント
- 公正証書と養育費保証制度の役割を知ろう
- 強制執行の手続きを理解しよう
- 「支払う相手」としての現実を認識しよう
養育費の未払いに備えるには、同居親がしっかりと体制を整えることが大切です。
支払わない別居親の責任はもちろんですが、「何もしなかった」同居親にも備えの意識が必要です。
経験者の声(一部抜粋)
- 「冷静に話し合う自信がなかったので、事前に準備を徹底しました」
- 「感情的にならないよう、第三者を入れて話し合いを行いました」
- 「養育費は払われなくなることを前提に、公正証書を作成。『私も社会もあなたを見ています』というメッセージにもなると感じた」
- 「離婚当時(8年前)は養育費保証制度がなかった。もしあったらすぐに入っていた。支払いが時々遅れることもあったが、義母がいたため払われていた。でも、義母が亡くなった後は不安になり、途中からでも保証に加入した」
大切なことは「離婚時に備えること」
公正証書と養育費保証制度を同時に準備するのが最も確実で安心です。
「うちは大丈夫」と思って後回しにし、支払いが滞ってから慌てても、その時点では加入できないこともあります。
保証制度に加入していれば、少なくとも2〜3年間は、元夫に代わって養育費が支払われます。
不測の事態にも、慌てず対応できる仕組みです。
アーカイブ視聴のご案内
当日は多くの反響をいただき、「アーカイブを見たい」という声が多数寄せられました。
アーカイブをご希望の方は、下記アンケートにご協力ください。
▶︎ [アンケートフォームはこちら]