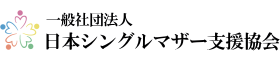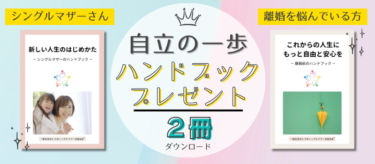シングルマザー支援、「語られない困難」を読み解き、「暮らせる年収」までを伴走する
女性の経済的自立について情報発信をしています。
■「腑に落ちました」「目からうろこです」■
私たち、ひとり親コンシェルジュが、相談者の方にとって「自分らしく」いられる生活になるために、いくつかの指標を持ち、そのことをヒアリングして読み解いていきます。
この指標はほとんどの方が、自分では気づいていないので、この指標を深掘りしていくと、不思議と本人がヒアリングされながら自分の考えを深掘りをすることで、納得していくのが表情でわかります。最後に言葉にすると「腑に落ちました」「目からうろこです」と言う方が多いです。
これが協会の相談の差別化される要因で、「語られない困難」を浮き彫りにできるんです。
■自分が知りたいことを教えてくれる場所が¨無い¨■
先日も行政のヒアリングを受けて、「なぜひとり親の方は相談をしないのか?」「相談する場所が無いと言うのか?」と。この答えは、相談場所が存在することはみんな知っていますが、¨無い¨と言うのは、自分が知りたいことを教えてくれる場所が¨無い¨という意味でしょう。私も離婚直後、役所に行っても答えがでないと感じたので、その後一度も相談には行ってないです。そこに相談場所があることは知っているけれど、そこに答えが無いと感じれば、もう相談場所は無いのと同じです。
この現象って、どこかで行政の窓口の相談対象者像と、実際の当事者像が変化しちゃったのかもしれませんね。今は福祉支援を受けたい人より、自立の方法を知りたい人の方が多いですが、私が行かなくなった理由も生活保護しか勧められなかったからですし。
福祉だと悪い意味で「今のままで」となりますが、多くの人が「生活を安定させる変化」に寄り添ってもらいたいと内心思っている。しかし、その言葉にはならないので、伝わらない。だからズレが生まれるのでしょう。
ここに「語られない困難」を読み解くスキルが必要となります。
■「語られない困難」を読み解き、「暮らせる年収」までを伴走する■
当事者も言語化できていないので、相談内容を明確に伝えることができない。相談を受ける側も、言語化された「語られる困難」のみで課題を受け取る。「語られない困難」がどちらにも見えていない中で、納得のいく答えはほぼほぼ出てこないです。
「語られない困難」を読み解き、「暮らせる年収」までを伴走する。これでほとんどのシングルマザーの自立支援は可能で、実現可能性が高まります。