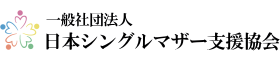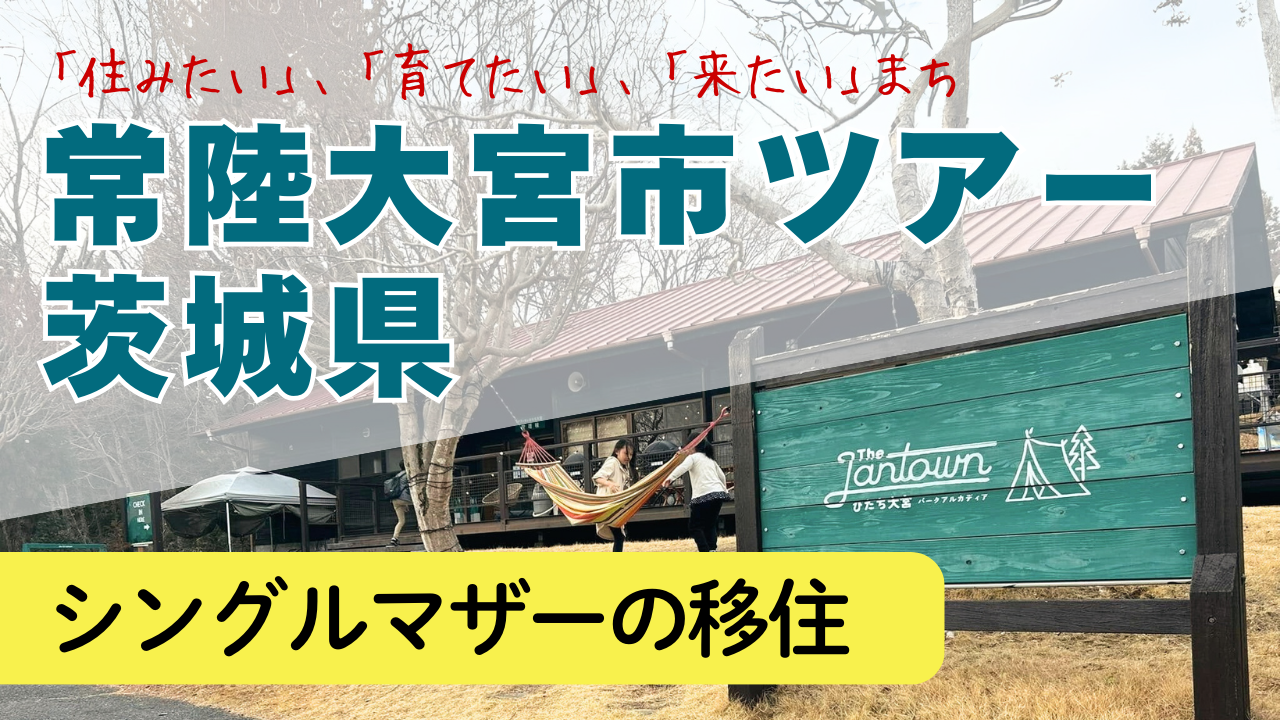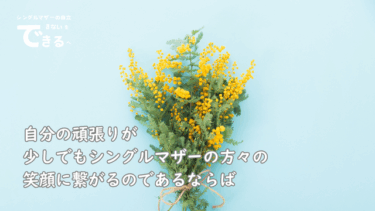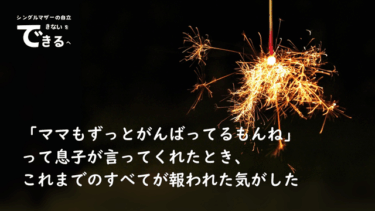【第2回】なぜ、「女性の自立」は進まないのか?
『女性の自立は社会の未来を変える 〜機運醸成の時代に生きる私たちへ〜』
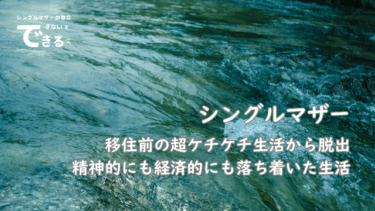
「自立は大切だ」と、頭では分かっている。
それでも現実には、自立に踏み出せない人がたくさんいます。
そして社会全体としても、女性の自立を本気で後押ししているとは言いがたい状況です。
では、なぜ“女性の自立”はここまで進まないのでしょうか。
■実は、社会も女性自身も「必要性に気づいていない」■
女性の自立が進まない背景には、社会の側と、女性自身の側、両方に“気づき”の欠如があります。
社会はまだ、「女性が自立することは、本人の選択の問題」であり、「こどもがかわいそう」「男が働けばいい」という性別役割分業意識の強いまま、無意識に思っている節がある。
つまり、“やりたいならやればいい。でも無理なら無理で仕方ないよね”という扱い。
これは、無関心ともいえるし、ある種のあきらめでもある。
一方、女性自身も、「自立しなければならない理由」にまで思いが至っていないケースが少なくありません。
家庭があるから、育児があるから、年齢が高いから。
気づけば「今のままでもどうにかなるから」と、変化を避ける選択が習慣になっている。
その結果がすでに、今の高齢女性の取り返しのつかない状況になっているとも言えます。
でも実際は、「どうにかなる」の中で、何も変わらず、時間だけが過ぎていくのです。
■自立は“強さ”じゃない。選択肢を持てる状態のこと■
ここで一度、定義を見直してみたいのです。
自立とは、「一人で何でもこなすこと」ではありません。
「自分の人生を、自分の意思で選べる状態」をつくることです。
選べない状態にあることが、依存を生み、不安を生み、時には無力感すら生みます。
でもそれが“当たり前”として放置されてきたのが、これまでの社会です。
■自立の必要性が“空気”になるまで■
今はまだ、「自立って必要なのか?」という段階にいる人が多い。
でも、これからは違います。“自立していることが当たり前”という空気を、社会全体に広げていく必要がある。
自立を「できる人だけがやること」にせず、「すべての人が目指すべきスタンダード」へと変えていく。
その第一歩が、「必要性に気づくこと」なんです。
次回は、「“日本はまだ自立のスタートラインにも立っていない”という現実」というテーマで、国際比較や社会制度から見える、私たちの現在地をお届けします。
自立を目指すすべての女性のための相談場所「ワタシのミライ相談」
会員登録時に「無料個別相談を希望しますか?」を、「希望します」で相談ができます。
相談は視野を広げ、未来を拡げ、何をするのか方法が見つかるという、あなた自身のひとつの行動です。