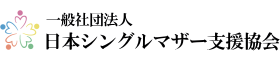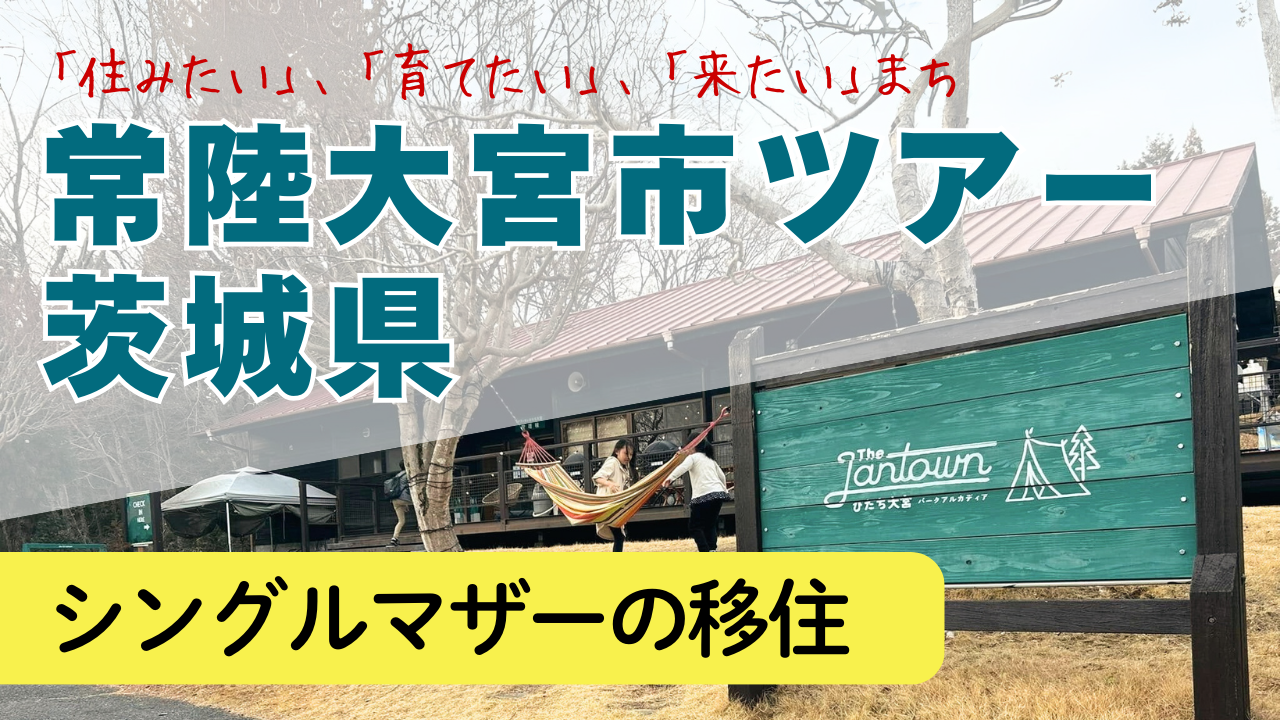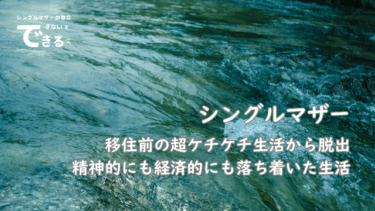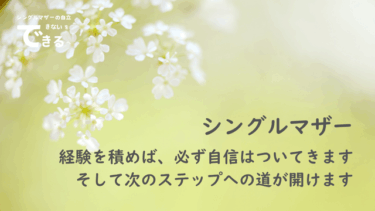【第3回】日本はまだ、自立のスタートラインにも立っていない
『女性の自立は社会の未来を変える 〜機運醸成の時代に生きる私たちへ〜』
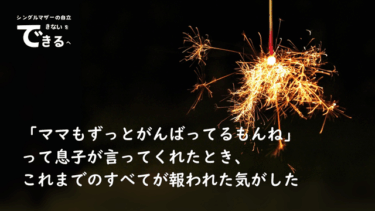
ここまで、「女性の自立は社会の土台であること」「それがなかなか進まない現状」についてお話ししてきました。では、日本は今、どこまで進んでいるのか?というと――正直、まだスタートラインにも立てていないというのが、私の率直な感覚です。
■ジェンダーギャップ指数、世界で125位■
世界経済フォーラムが毎年発表している「ジェンダーギャップ指数」をご存知でしょうか。
2024年の日本の順位は146か国中125位。
先進国とは思えない数字です。
特に、日本が大きく遅れを取っているのが「経済」と「政治」分野。
女性の管理職や役員の比率が著しく低く、政治の世界でも女性議員はごく少数派。
つまり、「意思決定の場」に女性がいない。
これでは、「女性が自立して活躍する社会」をつくるためのルールそのものが、変わるはずもないのです。
■社会が“女性の自立”に本気じゃない理由■
「女性も働けるように」と言われ続けてきたこの10年。
それでも実態が変わらないのは、社会が本気で“女性が活躍できる仕組み”を整えてこなかったからです。
たとえば、保育園の待機児童問題、時短勤務に対する職場の空気、管理職に上がりづらい評価制度。
制度があっても、文化が変わらなければ意味がない。
「整備した」という自己満足の影で、現実は置き去りにされたままです。
しかも、女性自身の中にも「責任ある立場は荷が重い」「今のままで大丈夫」といった空気が染みついてしまっていることもあります。この“遠慮”や“諦め”が、選択肢を狭め、将来のリスクを静かに積み上げていく。
その結果が、高齢女性の貧困問題の深刻化です。
配偶者がいる女性も含め、自立していないこと自体が、大きなリスクになっているのです。
■だから今は、「気づいた人から火を灯す」時期■
ここまで読んで、「なんだか重たいな」と感じたかもしれません。でも、私はこれを「絶望」ではなく「始まり」だと思っています。
社会はすぐには変わらない。けれど、“気づいた人”から動くことで、空気は確実に変えられる。
だから今は、「機運をつくる最初のステージ」なんです。
女性自身が、自分の人生を見つめ直すこと。
企業や地域が、女性の自立を支える仕組みに投資していくこと。
ひとつずつ、火を灯していくことが、やがて大きな光になります。
次回は、「制度があっても、自立は進まない。その理由はどこにある?」というテーマで、もっと深く、日本社会の“無自覚な壁”について掘り下げていきます。