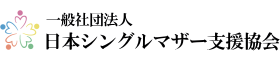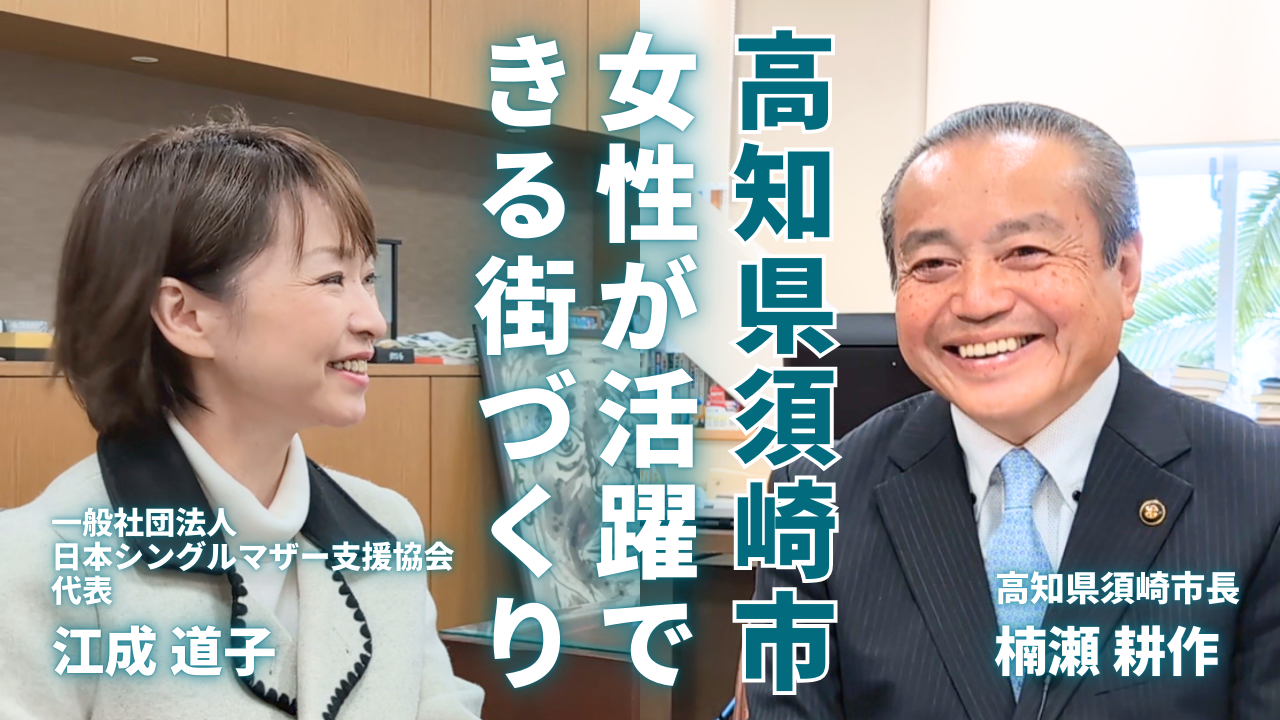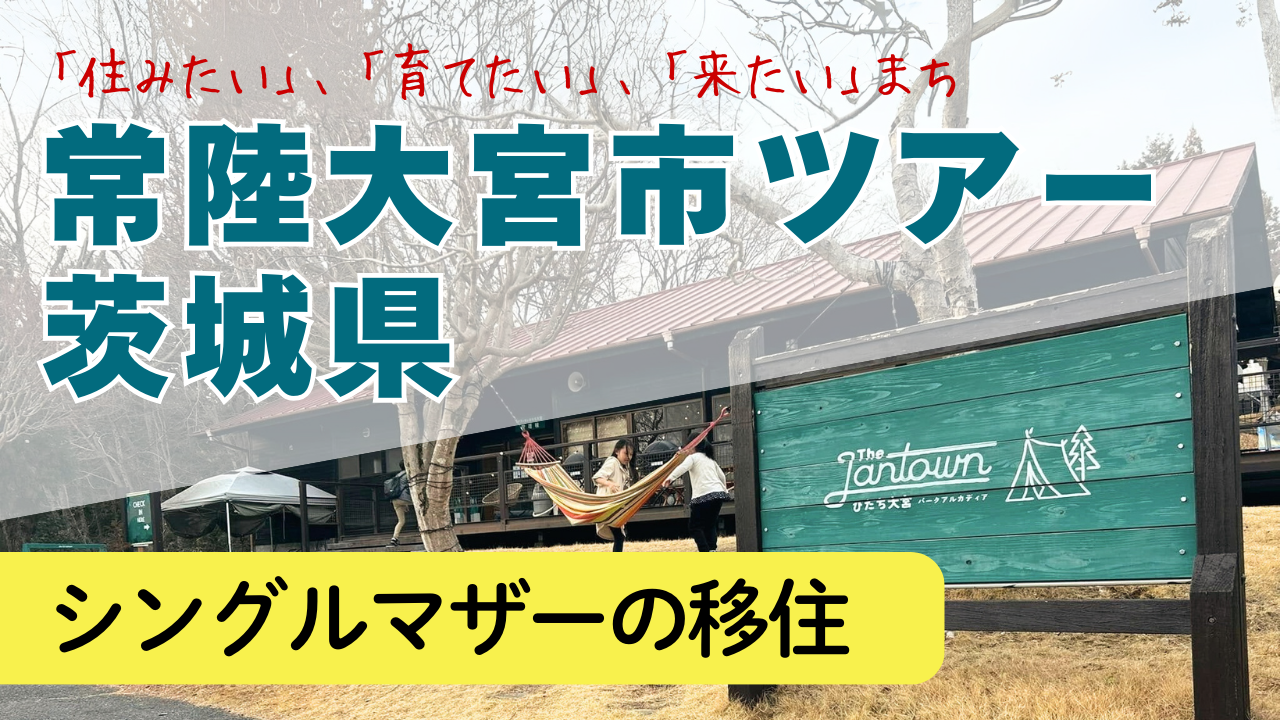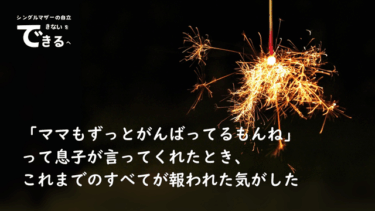【第4回】制度があっても、自立は進まない。その理由とは?
『女性の自立は社会の未来を変える 〜機運醸成の時代に生きる私たちへ〜』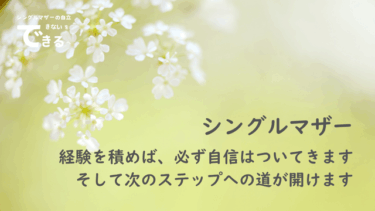
「女性が働ける制度は整ってきましたよね」そう言われるたびに、私は少しだけ違和感を覚えます。
確かに、産休・育休制度、保育園の整備、女性活躍推進法…制度は増えました。
でも、自立は進んでいない。
その“ズレ”こそが、今の日本社会の本質的な課題だと思っています。
■表面的な制度だけでは、選択肢にはならない■
制度が「ある」ことと、それが「使える」ことはまったく別の話です。
育休が取れる制度があっても、職場の空気がそれを許さない。
管理職を目指せると言われても、「女性はそこまで望まないでしょ?」という無言の圧。
「やっていいよ」という言葉の裏側に、「でも空気は読んでね」という目がある。
制度が整っても、文化が変わっていなければ、人は自由に選べません。
そして選べない社会は、結局のところ“自立を支える力”を失ってしまうのです。
■「無意識の壁」が、自立の芽を摘んでいる■
もっとやっかいなのは、誰かが悪意を持って妨げているわけではない、という点です。
“無意識”の偏見や、“当たり前”とされてきた価値観が、女性の選択肢をじわじわと狭めていく。
「出産後は仕事をセーブするのが普通」
「家庭を優先できない人は母親失格」
「夫の扶養内で働いた方が得だよ」
こうした“正論っぽい常識”が、何層にもなって女性を包み込む。
しかも、それを言っているのは、同じ女性であることも少なくありません。
■自立を支えるには、「仕組み」より「空気」が必要■
だからこそ、今必要なのは、「制度を整えること」ではなく、その制度を使える空気を育てることです。使った人が責められない空気。迷っている人の背中を押せる空気。失敗してもやり直せる空気。
制度は“入口”でしかありません。
その先でどう生きるかは、社会全体の意識によって左右されるのです。
自立は、制度だけでは実現しません。
むしろ、制度を使いやすくする空気こそが、
誰かの「一歩踏み出す力」になるのだと思います。
次回は、「母親が自立することが、子どもの未来を守る理由」
というテーマで、自立と家庭・子育てのつながりを見ていきます。
自立を目指すすべての女性のための相談場所「ワタシのミライ相談」
会員登録時に「無料個別相談を希望しますか?」を、「希望します」で相談ができます。
相談は視野を広げ、未来を拡げ、何をするのか方法が見つかるという、あなた自身のひとつの行動です。